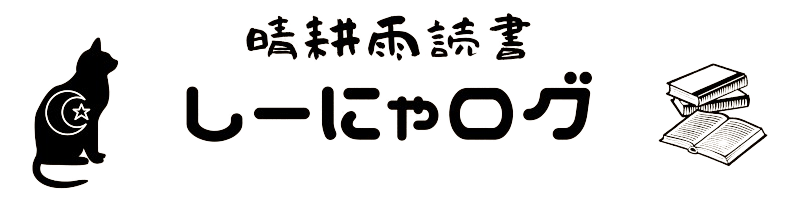酒は百薬の長
(さけはひゃくやくのちょう)酒は適量を飲めば健康に良く、どんな薬よりも効果のある薬であるという意味で用いられている。
ウィキペディア(Wikipedia) AIによる回答
現代においては「酒は百薬の長にあらず」という逆説的な言葉も生まれており、そのまま鵜呑みにするのは危険だとされている。
現時点において飲酒と健康の繋がりにおいて明確な確証はなく今なお研究が続けられているのが実情である
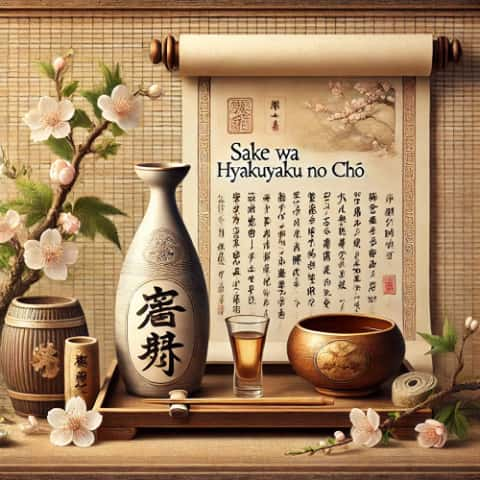
「“百薬の長”って本当に健康に良いの?」
古くから「お酒は百薬の長」と言われてきました。
仕事終わりに飲む一杯、仲間との語らいの時間――心がほぐれる瞬間です。
特に私たちのように体を使って働く農業者にとって、晩酌は1日の終わりを締めくくる小さなご褒美にもなります。
しかし近年、健康面でのお酒の評価は大きく揺れています。
実は以前、このテーマで記事を書いたことがあります(※前回の記事はこちら)。
おかげさまで多くの方に読んでいただきましたが、「もう少し根拠やデータも見たい」「健康的な飲み方が知りたい」といったご意見もいただきました。
健康情報があふれる現代、「適量なら健康に良い」という意見と、「少量でもリスクがある」という正反対の見解が並び、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
ということで今回は、国内外の研究データや公的機関の見解、そして農家としての実感を交えて
“お酒は本当に健康に良いのか?”をもう少し深掘りしてみます。
今回は、最新の研究データと農家としての実感を交えながら、「お酒のメリットと落とし穴」を冷静に見つめ直し、どう付き合っていけばよいのかを考えます。
賛成派の意見:適量なら健康に良いというデータも
一部の研究では、「少量のアルコール摂取が健康に好影響を与える」とする報告もあります。
- ✅ 心血管疾患のリスク低下
ハーバード大学公衆衛生大学院の研究によると、1日1杯程度の赤ワインなどの軽い飲酒は、HDL(善玉)コレステロールを上げ、心疾患の予防に役立つ可能性があるとされています。 - ✅ ストレス軽減と社交的効果
適量の飲酒はリラックス効果や、コミュニケーションの円滑化につながることも指摘されており、精神的な健康にも一定のプラス面があるという見方もあります。 - ✅ 心臓病リスクの低減
適量の飲酒は心臓血管系疾患のリスクを低減する可能性があります。特に赤ワインに含まれるポリフェノールが心臓に良い影響を与えるとされています。 - ✅ 血中コレステロールの改善
適量の飲酒はHDLコレステロール(善玉コレステロール)を増加させ、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を低下させる効果があります。 - ✅ 血管の拡張
適量の飲酒は血管を拡張させる効果があり、血流を改善することが期待されます。 - ✅ 血糖値の改善
適量の飲酒はインスリン感受性を改善し、血糖値のコントロールを助ける可能性があります。 - ✅ 炎症の軽減
適量の飲酒は炎症を抑制する作用があり、関節炎などの炎症性疾患のリスクを軽減する可能性があります。
特に、自然相手に孤独になりがちな農業という仕事では、人と交わる場としての「飲み会」が精神的な支えになることもあります。
① ハーバード大学公衆衛生大学院(HSPH)
研究名:Moderate Alcohol Consumption and Health Outcomes
発表年:2020年(および継続研究)
要点 :
- 1日1杯程度の中程度の飲酒(男性:1~2杯、女性:1杯まで)は、冠動脈性心疾患(心筋梗塞など)や糖尿病のリスクを下げる可能性がある。
- 「完全に断酒」している人よりも、適量飲酒者の方が死亡率が低い傾向があった(ただし、他の生活習慣の影響を除外しきれていないという批判も)。
出典:
Harvard T.H. Chan School of Public Health – Alcohol: Balancing Risks and Benefits
② 日本医師会雑誌(JMAJ)に掲載された国内研究
研究名:飲酒習慣と心疾患リスクに関する日本人データ分析
要点:
- 日本人約4万人を対象にした疫学調査では、「週に3〜4日、1日1〜2合の日本酒を飲む人」は心筋梗塞や脳卒中の発症リスクがやや低いという傾向が見られた。
- ただし、飲酒頻度が増えると「高血圧」のリスクは上昇傾向に。
反対派の意見:依存や健康被害のリスク
一方で、近年では「どんな量でも健康に良いとは言えない」という研究が急増しています。
- ❗ 少量でもがんリスクが上がる可能性
WHO(世界保健機関)は2023年に、「いかなる量のアルコールも健康に害を与える可能性がある」との立場を強めました。特に食道がんや肝臓がんとの関連性が強調されています。 - ❗ 肝機能障害・依存症のリスク
習慣的な飲酒が続くことで、肝臓に負担がかかり、「気づかぬうちに肝機能が落ちる」ケースは少なくありません。さらに、日常の疲れやストレスから「晩酌→常習化→依存」へと移行してしまうリスクも見過ごせません。 - ❗ 健康リスク
過剰な飲酒は肝臓疾患、高血圧、心臓病、脳卒中、消化器官への影響などのリスクを高める可能性があります。 - ❗ 依存症リスク
長期間にわたる過剰な飲酒は、アルコール依存症のリスクを高めることがあります。 - ❗ 社会的影響
酩酊状態での振る舞いやアルコールによるトラブルが社会的関係や仕事に影響を与えることがあります。
ほろ酔い気分でも理性が緩むため普段とは違う正常な判断が難しくなります。 - ❗ 交通事故
酒気帯び運転は交通事故の原因となり、重大な結果をもたらす可能性があります。
年々飲酒運転の厳罰化が進んでいますが、やはり少しの油断で運転してしまうこともありえます。 - ❗ 妊娠中のリスク
妊娠中の飲酒は胎児に悪影響を与えるおそれがあります。 - ❗ 体重増加
アルコールにはカロリーが含まれており、過剰な摂取は体重増加を引き起こす可能性があります。
また、アルコール摂取により塩辛いものや味の濃いものを食べたくなり、食欲増進も合わさって結果的に脂っこいもの等を大量に食べてしまうことになり得ます。
また、アルコールは睡眠の質を下げ、疲労回復を妨げるという点も、体を酷使する農業においては特に重要なポイントです。
① WHO(世界保健機関) / IARC(国際がん研究機関)
声明:No level of alcohol consumption is safe for our health
発表年:2023年1月
要点:
- アルコールはグループ1の発がん物質であり、「がんを引き起こすことが明らか」と分類されている。
- 少量の飲酒でも食道がん・乳がん・肝がんのリスク上昇が確認されており、「安全な飲酒量は存在しない」と明言。
- 特に東アジア人(日本人を含む)の多くはアルコール代謝酵素(ALDH2)が弱く、がんリスクが高まりやすい。
出典:
WHO Europe – No safe amount of alcohol consumption
② 英医学誌『The Lancet』に掲載された国際共同研究
研究名:Global Burden of Disease Study(GBD 2016)
発表年:2018年
要点:
- 世界195カ国、1500以上の研究データを統合。
- 「健康にとって最も安全なアルコール摂取量はゼロ」という結論を提示。
- 少量でも事故・自殺・がん・肝疾患のリスクが高まることが明確になった。
出典:
Lancet. 2018;392(10152):1015-1035.
Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016
研究結果の全体像
| 観点 | 賛成派 | 反対派 |
|---|---|---|
| 主張 | 適量なら心臓病リスク低下、ストレス軽減に有効 | 少量でもがん・肝疾患・依存症など健康被害あり |
| 研究対象 | 多くは欧米人中心、日本人にも当てはまるかは注意必要 | 世界規模でのメタ解析やWHOの統一見解あり |
| 結論傾向 | 「量と頻度を守れば恩恵あり」 | 「どんな量でも安全とは言えない」 |
農家としての実感:飲酒とのリアルな付き合い方

私自身、農家として毎日汗をかきながら働いています。
夏場の炎天下での作業後、冷えたビールの一口はまさに「命の水」に感じられることもあります。
ですが、それと同時に「飲み過ぎた翌日のだるさ」「思ったほど回復していない体調」に気づいた経験も数多くあります。
農業は自営業であり、体が資本です。
誰かが代わりにやってくれる仕事ではありません。だからこそ、「飲みたいけど、飲みすぎない」「うまく付き合う」ことが必要だと日々実感しています。
私が意識していることの一例を挙げると:
- ゆっくり少しずつ飲む
- 晩酌時は必ず水を一緒に飲む
- 空腹では飲まない。まず野菜中心の軽い食事をとる
どれも簡単なことですが、体の調子が全然違います。
賢く付き合うための3つのポイント
お酒は、完全に「敵」でもなければ「味方」でもありません。
大切なのは、自分の生活リズムや体調に合わせて、うまくバランスをとることです。
以下の3つを意識することで、健康的なお酒ライフに一歩近づけるかもしれません。
飲むなら“量”より“質”
アルコール度数や量ではなく、「どんな気持ちで、どんな場面で飲むか」が大切です。惰性ではなく、楽しむための一杯を意識しましょう。
肝臓を助ける“食材”を意識する
ごぼう、しじみ、緑黄色野菜など、肝臓をいたわる食材を意識的に摂ることで、アルコールの代謝がスムーズになります。
“飲まない日”を作る勇気を持つ
飲む習慣は、気づけば生活の一部になってしまいます。意識的に休肝日を設けることで、自分の体調の変化にも気づけるようになります。
まとめ:酒は飲んでも飲まれるな

冒頭にも書いてありますが、ここまで研究の進んだ現代においても明確に良し悪しは判断できていません。
しかし、飲んでない人は敢えて飲酒を始める必要はなく、飲酒する人も程々の適量で済ます事が正解であることは間違いないと思います。
お酒は、人生を豊かにする道具のひとつです。
しかし、それは自分の身体としっかり向き合ってこそ。
我慢して、ストレス溜めながら日々の楽しみが無くなる事は精神的にも辛く
それで病んでしまったら元も子もありません。
農家という仕事は、「自分の健康=仕事の成果」と直結する職業です。
だからこそ、飲むなら、知識と意識を持って賢く付き合いましょう。